こんにちは。Horyです。
前回の記事では化学結合について、金属結合・イオン結合・共有結合についての原理と違いを解説しました。
この中で金属結合について解説し、金属の性質に関して浅く解説しました。
今回の記事では、金属の性質に関して以下に示すことに焦点を当てて解説します。
- 電気・熱伝導性
- 展性・延性
- 金属光沢
- 融点
- 密度
今回も頑張りましょう。
電気伝導性・熱伝導性
前回の記事でも解説しましたが、復習も兼ねてもう一度解説します。
- 金属元素は電気陰性度が小さい(電子を拘束しようとしない)
- 金属元素は空軌道をたくさん持つ
- →だから、金属結晶内を電子が自由に動ける→自由電子
- →自由電子が熱や電気を運ぶ→電気伝導性・熱伝導性が高い
ちなみに、熱伝導性・電気伝導性ともにAg(銀)>Cu(銅)>Au(金)>Al(アルミニウム)の順になっています。
また、温度が増加すると共に陽イオンの動きも激しくなります。すると、電子の動きを陽イオンが妨げるため、温度の上昇と共に電気は流れにくくなります。
物理の記事になりますが、こちらを見ていただくと物理的にもしっくりくると思います。
展性・延性に富む
続いて、金属が展性や延性に富む理由ですが・・・
- 外から力を加える
- 陽イオンがすれてしまうが・・・
- 自由電子は金属結晶中を自由に移動
- クーロン力によりずれた陽イオン(金属イオン)を引きつける
- だから、伸ばしたり広げても壊れない
金属光沢がある
金属光沢がある理由ですが、これは、金属中の電子がほぼ全ての可視光(人間に見える光)を反射するからです。(全ての可視光を反射すると目に入る光は白くなる)
ここで、疑問が生じます。
「金(Au)や銅(Cu)は色がついてるじゃん」という疑問です。
そもそも、色を認知するというのはどういうことかというと、物理の記事でも書きますが、光の正体は波と考えることもでき、波長(波の長さ)があります。光が目に入ってくるときに波長によって我々が認知する色は違ってきます。
上の説明を踏まえると、金(Au)や銅(Cu)は特定の波長の光しか反射しないと言うことではないでしょうか?
無機化学で結晶や化合物の色や借イオンの色を必死に暗記している人がいますが、暗記は悪いとは言いません。
ただ、色が違って見える原理を理解することで同じような暗記でも理解は違ったモノになってくるのではないでしょうか?
金属の融点
続いて、金属の融点についてデス。
基本的に典型元素と比較して遷移元素の融点の方が圧倒的に高いです。
- 典型元素より遷移元素の方が高融点
- 典型元素より遷移元素の方が価電子多い
- クーロン力を考えると・・・
ここまで来たら考えれば分かると思いますが、物質が状態変化すると言うことは、物質中に働く結合や力を断ち切ると言うことです。
価電子の多い金属の方がクーロン力の大きさは大きいので・・・
金属の密度
金属の密度に関してです。金属は基本的に高密度です。
理由としては、1つの金属原子の周りにできるだけ多くの金属原子が配置した方がより多くの金属原子が金属結合します。
例えば、1つの金属原子の周りに3つよりも6つ金属原子が配置した方が金属結合が多くなり、自由電子の数も多くなることで金属としての性質がより強くなります。
次回の記事で出てきますが、金属結晶格子で1つの金属の周りに隣接する原子(配位子)が8個とか12個なのはこのためです。
今回の記事はこれで終わります。金属の性質とそのようになる理由を理解しておいてください。
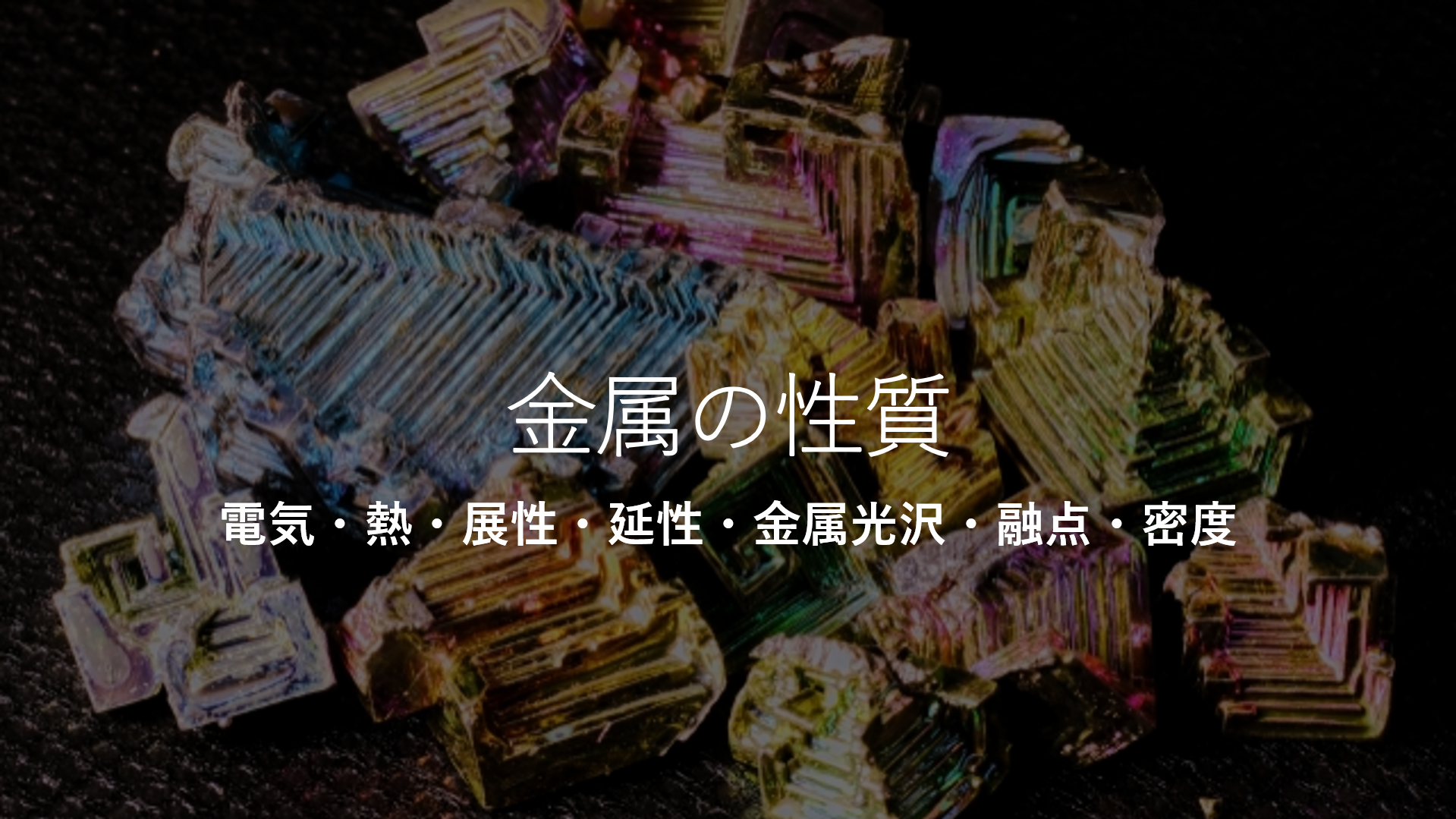

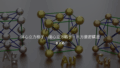
コメント