こんにちは。Horyです。
前回の記事では酵素に関する基礎的内容と基質特異性に関して鍵と鍵穴の例え話を用いて解説しました。
今回の記事では酵素の反応とミカエリスメンテン式に関して解説しようと思います。
今回はかなり発展的な内容になりますが頑張りましょう。
ミカエリスメンテン式
ミカエリスメンテン式について解説します。
反応式に出てくる文字を以下のように定義します。
- X;酵素 (鍵穴)
- Y;基質 (鍵)
- XY;酵素-基質複合体 (鍵穴に鍵が入った状態)
- Z;生成物
酵素の反応は基本的に二段階です。

- 一段目の反応の平衡定数;K1
- 一段目の反応速度;v1
- 二段目の反応速度;v2
- 全体の反応速度;V
これらについて式を立ててまとめます。

ちなみに、全体と二段目の反応速度が等しいと見なせるのは一段目と比較して二段目の反応速度が著しく遅いからです。
そのため、全体の反応速度は比例定数kとして以下のように表せます。

- 一段目の速度;Y(基質)がX(酵素)に入ってXYが出来るまでの時間
- 二段目の速度;XY(複合体)がX(酵素)とZ(生成物)に分離するまでの時間
- 全体の速度;Y(基質)とX(酵素)が反応してX(酵素)とZ(生成物)になるまでの時間

ちなみに[X’]を酵素の全体濃度としています(酵素に関係ある物を酵素の全体濃度とする)。
酵素の濃度は常に一定です。
何故なら、酵素は触媒として利用されます。
そのため、反応の速度を変えることはあっても反応自体には一切の関与をしないので、反応前後で酵素の総量が変化することはあり得ません。

上の紫色の式のことをミカエリスメンテン式と呼んでいます。

- 基質濃度[Y]が小さい;反応速度は基質濃度に比例
- 基質濃度[Y]が大きい;反応速度は一定
酵素には以下の特徴があります。
- 基質特異性が存在
- 酵素は特定の基質に反応する (前回の記事で話した)
- 酵素の最適温度
- 温度上昇で分子運動により立体構造が崩れるから
- 立体構造が崩れること・・・変性
- 働きが失われること・・・失活
- 酵素の最適pH
- pHが立体構造に影響する
- NH3イオン/COOイオンがpHにより変化する

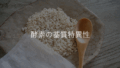
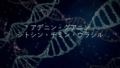
コメント