こんにちは。Horyです。
前回の記事では熱力学の基本的な考え方に関して話しました。この記事の中で系について話しました。
復習ですが系とは複数の粒子が入った空間のことで、熱力学ではこの系に適用する物理法則を当てはめて系全体の未来をマクロ的観点から予言する学問です(逆にミクロ的観点から予言する学問を熱統計力学という)。
今回は高校物理で考えることになる熱力学の系に関して話すと共に熱平衡原理に関してまとめます。
今回も頑張りましょう。
熱平衡状態と系
熱平衡状態とはどういう状態なのかを説明します。
言葉で説明しても分からないと思うので、熱平衡でない状態から熱平衡状態に遷移する過程を説明します。
- 温度差のある系が接触 (熱平衡でない)
- 低温→高温で熱が移動
- 時間が経つと熱の移動が停止
- 2つの系の温度が等しくなる (熱平衡状態)
高校物理で出てくる系は熱平衡状態の系しか出てきません。
どういうことかと言うと、複数の系(熱平衡がそれぞれの系で成立)を接触させて新たな熱平衡状態に移動するまでに「温度・圧力・体積」がどうなるのかというテーマの問題が出てきます。
ちょっと注意なのですが、複数の系を接触させて新たな平衡状態に移動する過程は平衡状態ではありません。
そのため、「途中で非平衡状態になる系の未来は予測できないのでは?」と思うかもしれませんが、ちょっとしたトリックがあります。このトリックには別の記事で解説します。
また、系には単純系と複数系というものがあって・・・
- 単純系・・・中が仕切りとかで分断されていない均一な系 (温度とかが偏ってない)
- 複数系・・・単純系が合体してできる系
高校の熱力学では主に2つの単純系を接触させ、複合系にして十分に時間が経った後、複合系が熱平衡状態になるまでがテーマの問題が出されます。
熱平衡原理
熱平衡原理とは、「外から何の影響も受けない系は十分に時間が経つと全体としては熱平衡状態になる」という原理のことです。
ただ、1つ注意してほしいのがあくまで全体として熱平衡状態になっていると言うだけで、切り取って拡大してみると熱平衡状態ではないことを覚えておいてください。
熱力学では全体として見ても系が変化している場合は非平衡状態と言います。
非平衡状態の法則は僕が知る限りでは未完成だと思います (一部に条件の縛りをつけた法則なら完成されているかもしれないが・・・)。
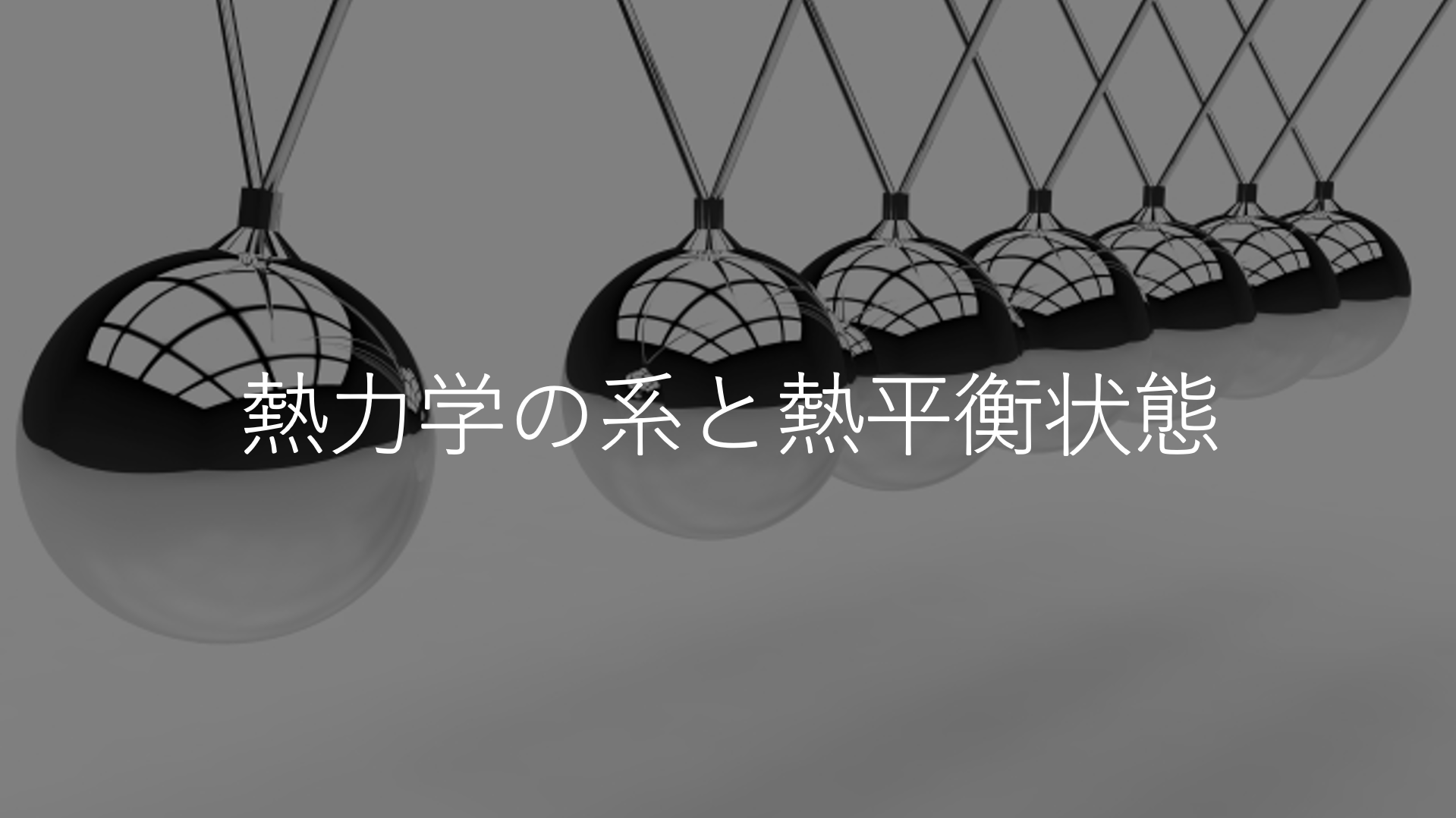
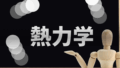
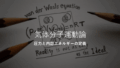
コメント