こんにちは。Horyです。
前回の記事では気体分子運動論に関して考えると共に圧力や内部エネルギーの定義を解説しました。
圧力と内部エネルギーは以下のように定義できます。
- 圧力・・・粒子が壁に与える時間平均を壁の面積で割り算した値
- 内部エネルギー・・・全粒子の運動エネルギーの和
今回の記事では熱力学で出てくる壁の種類と熱力学第零法則について解説します。
熱力学に出る法則は第零~第三までありますが、第零法則は見落としやすい人が非常に多いです(当たり前すぎることだからというのもある)。
今回も頑張りましょう。
熱力学で出てくる壁
熱力学で出てくる壁とは孤立系と孤立系を隔てるモノだと考えてください。
系に関してはこちらの記事に書かれているので読んでおいてください。
熱力学では以下の2つの壁が出てきます。
- 熱を通さない壁
- 孤立系と孤立系で熱が移動しない
- 粒子が入った空間自体が熱を通さない・・・断熱系
- 熱を通す壁 (この壁は見えないこともある)
- 孤立系と孤立系で熱を通す壁
- 孤立系と孤立系の接触 (熱接触)→これは壁がなくても孤立系が混ざれば熱接触
熱力学第零法則
熱力学第零法則とは「単純系複数を熱接触させた系が熱平衡状態だったら単純系の温度は全て等しい」という法則です。
まぁ、当たり前のことですが、見落としている人がかなり多いです。
ちなみに、熱接触をさせて熱平衡状態へ至る過程を解説すると・・・
- 温度差のある孤立系を熱接触
- 高温系から低温系に熱が移動する (普通は熱平衡状態でない)
- 2つの孤立系の温度が等しくなる(熱の移動が起きない→熱力学第零法則)
ちなみに、高温から低温に熱が移動することはありますが、自然界では低温から高温に熱が移動することは絶対にありません。
そのため、上の手順を逆にして、熱平衡状態から温度差がある最初の状態に戻すのは絶対に無理です。
これは覚えておいてください。
また、例え話で解説すると、熱々のマグマに水を一滴入れたとしてもマグマの温度は変化しないと見ることができます。
このように、熱接触をさせて平衡状態にしても前後で温度が変わらない系を熱浴と呼んでいます。

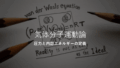
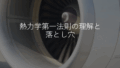
コメント