こんんちは。Horyです。
皆さんは自分が行こうとしている大学の過去問を解くと思います。
私はこれまでに多くの学生は過去問を解くときの解き方を勘違いしているように思います。
と言うのも、「過去問に出てくる全ての問題を解ける学力をつけなければならない」という固定観念にとらわれているように感じます。
この考えは半分正しいですが半分間違いだと私は考えています。
今回の記事では過去問を解くときにどういう観点を重視するべきかという戦略を解説していきたいと思います。
今回も頑張りましょう。
過去問と見るべきポイント
自分が志望する大学の過去問に取り組む前に必ず見てもらいたい事項は以下に示すとおりです。
- 過去問の全体と科目ごとの合格者平均点
- 過去問の全体と科目ごとの合格者最低点
- 科目ごとの大問得点率 (情報が載っていれば)
上の3点を必ず頭に入れておく必要があります。
理由を個別に説明していきます。
過去問の合格者平均点/最低点
最初にも言いましたが、多くの学生は「過去問に出てくる全ての問題を解ける学力をつけなければならない」という固定観念にとらわれていると話しました。
そして、この考え方は半分正しくて半分間違っていると言うことも話しました。
というのも、東大や京大・旧帝大医学部などの一部の最難関理系学部の数学の合格者平均点は100点中40点程度ということも普通にあります。
100点中40点というと、大問5個あれば2完分の点数があれば勝てるということです。
どういうことかと言うと、合格者平均点が大問5個中の2題分の点数の試験で全問正解するために勉強時間とかのリソースを費やすことが賢いのか?と言うことです。
- 合格者平均点を見る・・・自分が過去問でどの程度の点数を取れば良いのかの把握
- 合格者最低点を見る・・・自分が過去問で何点未満を取ってはいけないかの把握
そして、過去問が終わったら自己採点をすると思いますが、自己採点が終わったら採点結果が合格者平均点と最低点からどの程度離れているかを分析してください。
その後、残された有限の時間(リソース)をどの科目にどの程度配分するかを決めて戦略を立ててください。
ただ、補足ですが、大学の受験を突破するための基礎学力は必要です。
そのため、どのような問題が出てきたとしても対応できるような最低限の学力はつけておくべきで、そのためにはがむしゃらにやらないといけないときもあります。
この点が先ほどの考え方の半分正しい部分です。
科目ごとの大問得点率
皆さんは試験で不合格になる理由は分析できていますでしょうか?
これは多くの人が勘違いしていることでもあります。
- 勘違い・・・難しい問題を解けなかったから
- 正しい認識・・・多くの人が解けている問題が解けなかったから
試験で不合格する理由は「難しい問題を解けなかったから」ではありません。
「多くの人が解けている問題が解けない」ために不合格になるのです。
だから、科目ごとの大問得点率が開示されているのであれば自分の自己採点結果を見て何が解けていて何が解けていないかを分析してください。
回答率が50%以上の問題を解けていないのであれば要注意です(その問題が何で解けないのかを重点的に分析しましょう)。
重要な事ですが、試験で明暗を分ける問題は難しい問題でなく簡単な問題です。
つまり、簡単な問題で満点を叩き出すような学力が必要なのです。
ただ、1つ注意点ですが、世の中には普通の人が解けないような鬼門でもヒョイヒョイ解いてしまうような人もいます。
そのような人は先ほどの合格者平均点が40点程度の点数でも満点を取ってきます。
そんな人がいることも事実ですが例外(外れ値)だと思ってください。統計は何でもそうですが、外れ値というのは必ずあります。
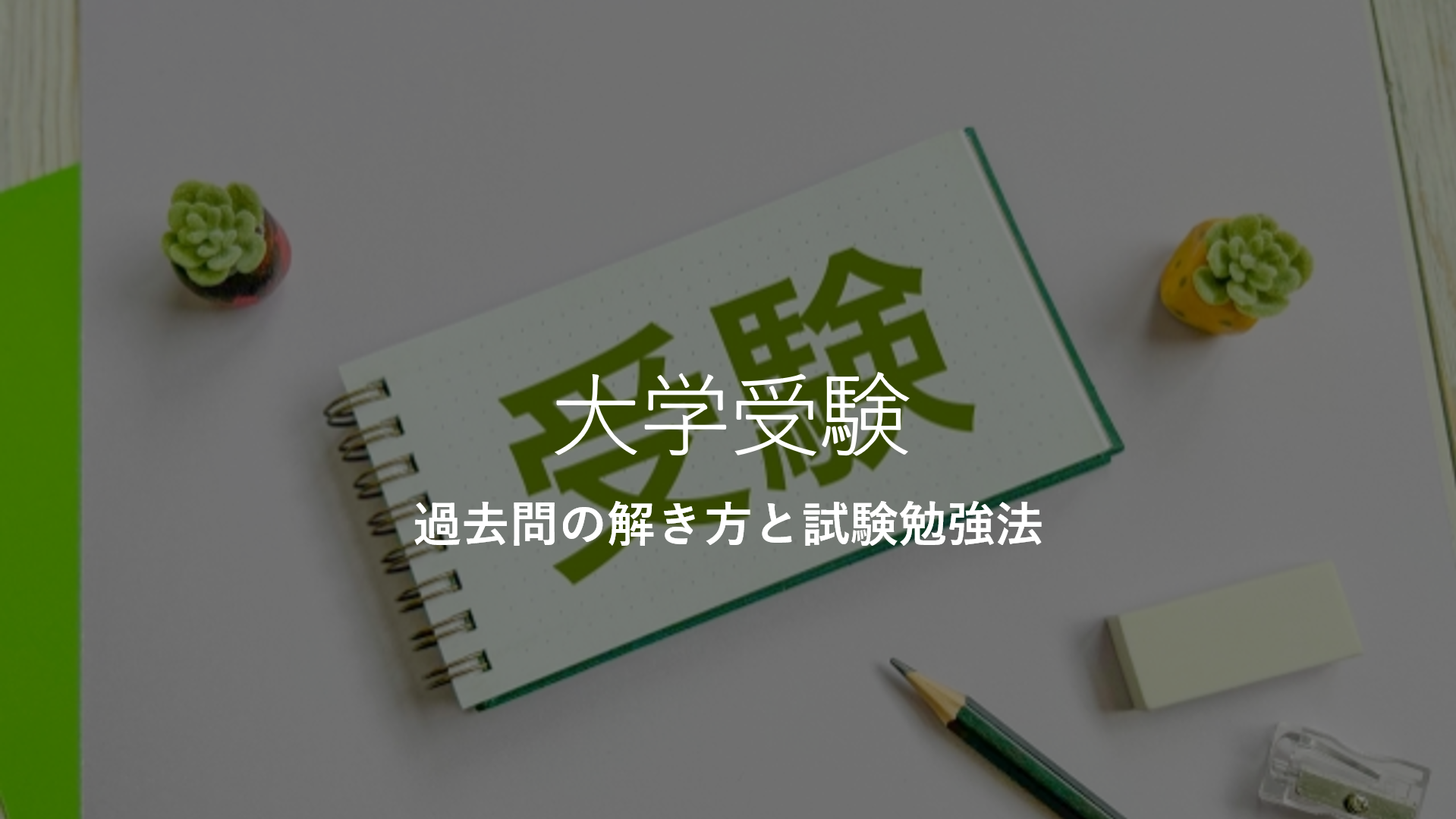
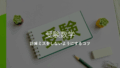
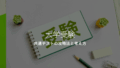
コメント